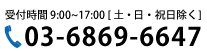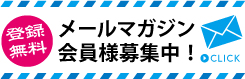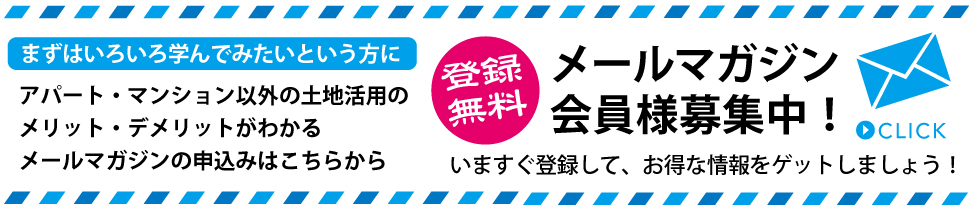■土地活用時に知っておきたい専門用語
■利回り(土地活用&不動産投資)土地活用の利回りは一般に、月額家賃×12÷建築費総額で提案されることが多い。これに対して、不動産投資サイトなどに記載されている利回りは月額家賃×12÷土地建物の購入額(表面利回り)が一般的である。さらにREIT(不動産投資信託)で表示されているものは年間の純収益(経費支払後・償却前・金利支払前・納税前)÷土地建物の購入額となっている。業界に応じて分子と分母が異なることに注意を要する。
■賃貸募集の強化(住宅)近時、少子高齢化及びアパートマンションの建築増により空室率が増大傾向にある。必要になるのは差別化である。他の物件との比較において自分の物件が募集家賃水準以外になにが優位であるかを検討する必要がある。駅距離や部屋の高さ、構造など後から変えられないものは改善する方法に乏しいが、内装や設備などはリフォーム・リノベーションなどにより改善する手段がある。数字での改善方法は、家賃水準の減額、礼金・更新料のカット、フリーレントの設定、賃貸募集会社への広告料上乗せなどがある。また、営業マンへの内覧会実施や募集図面のカラー化、家具の設置(モデルルーム化)等のプロモーション強化策などがある。
■入居審査(住宅)外国人や生活保護者などの増加により賃借人の属性に応じた入居基準を設定するべきであり、管理会社にお任せする以外に自分が良いと考える基準を設けることが大事である。単に外国人だから不可とすると稼働率確保には厳しすぎるという説もあり。築年や立地などの競争力に応じて弾力的な設定が求められる。
■家賃保証(住宅)賃借人からの家賃の入金がない場合に家賃保証会社が立て替えて入金してくる仕組み。「連続○か月滞納後に入金」とか、「原状回復費用の保証はしない」など、家賃保証会社に応じて保証する範囲や基準が異なる。原則的に家賃保証会社が立て替えをした場合には管理会社は直接賃借人と連絡を取るケースは少なく、家賃保証会社を介して請求していく場合が多い。
■原状回復(住宅)賃貸住宅における賃借人退去時の原状回復費用を定める際、賃借人が入居していた年数に応じて賃借人とオーナーの負担割合が変わる「東京ルール」が採用されている。国土交通省が原状回復について定めるこの「東京ルール」では、賃借人が支払う賃料には経年劣化や通常の損耗分に相当するものが含まれており、それを大家に支払っていると整理されている。したがって賃借人の負担については、年数が長いほど賃借人の負担割合を減少させる考え方が採用されている。結果として大家の原状回復の負担割合は賃借人の契約年数が長くなるほど大きくなる。
■原状回復(事務所)事務所の原状回復は住居の場合と異なり「東京ルール」の適用がなく、法人利用として不特定多数が出入りする可能性もあることから、テナントが退去する際は、契約時・入居時に定めた「原状」に戻して大家に明け渡すように定められていることが一般的である。事務所の「原状」は入居した状態を表すことが一般的であり、据え付け済みの空調やOAフロアのある状態(場合によってはPタイル仕上げ)が多い。その一方で、OAフロアをテナント側で新設したり床を上げるなど特殊工事を施した場合には退去時にどのようにするかトラブルになりやすいため、契約時に「原状」復帰をどうするべきか決めておくことが理想的である。可動しやすいパーティションなどはテナントが撤去していくことがきわめて一般的であるが、強固に壁・床に接続する間仕切壁をテナントが設置した場合などは、退去時にどのようにするのかについては入居時にしっかり決めておきたい。
■原状回復(店舗)店舗の原状回復はトラブルになりやすい。店舗の「原状」はオーナーが提供する資産によって変化する。原状を「スケルトン状態(設備や内装がほぼ何もない状態)」にしてテナント募集すると、テナントは資産を持ち込まなければいけない設備や内装などの負担が大きくなる。一方、空調設備など汎用性のある設備や内装をオーナー側で作りこむとテナントは負担が楽になり出店しやすくなる。多くの資産をテナントに持ち込まれるとテナントは退去時に解体費用が嵩むことになり、オーナーは事務所・住居の場合に比べて、解体されないまま廃業されるという「解体未完了リスク」を負っている。したがって、その解体費用を保証金で担保していると考えることが多い。なお、テナント募集時に、競合が設定する資産区分に対抗するため、自分の募集物件についても提供する資産が影響を受ける場合がある。その結果「原状」についても変化することになる。世間的にはいろんな資産区分で募集するオーナーがいるが、あまり多くを提供したくないのが一般的である。一方、大手テナントチェーンは資産区分の「標準系」を自社で決めていることがある。そのため、テナントの出店意向がはっきりしていても資産区分の負担につき両者で折り合いがつかず賃貸借契約に至らない場合もある。「原状」は図面・表などで作成して賃貸借契約書に添付しておくことが望ましく、退去時の原状回復工事を決める際に必ず役に立つ。
店舗
■賃貸借契約の年数業態や建物形状に応じて契約する種類と年数が大きく異なる。駅前ビル内の飲食店は設備を持ち込んで開業することが多いため、設備の償却のために7~10年程度の契約を希望してくることが多いが、街中のドラッグストアや物販店などはあまり設備を持ち込まないため2~3年程度でも契約するケースがある。一方で郊外型ロードサイド店舗の場合で新築時からオーナーが土地活用して建築する場合は双方とも長期で契約したいというニーズが働き20年契約になることが多い。
■資産区分店舗の場合、オーナーが設置・保有する資産とテナントが設置・保有する範囲が異なる。この区分を明確にしたものが「資産区分」であり、賃貸借契約書の締結と同時に作成することが望ましい。一般に、オーナーが保有する資産をA工事(A区分)、テナントが仕様を決めて費用を負担しオーナーが保有するというのがB工事(B区分)、テナントが購入して設置・保有するのがC工事(C区分)である。これらを定めることにより原状回復工事における「原状」の定義が定まる。つまりB工事はオーナーが保有するためテナント退去時取り出すことができないが、C工事部分はテナントが外して退去することになる。その他、修繕範囲を決める「修繕区分」、部品や一部設備を入れ替える範囲を定める「更新区分」、どちらが管理をするかを決める「管理区分」などがある。
■ペナルティテナントが契約期間を満了する前に解約して退去する場合、オーナーに対する違反金の支払いを行うように定めるのが「違約金(ペナルティ)設定」である。テナント仕様で新築している場合には長期でテナントに借りてもらうことが前提となるため、期間内での解約については相応の違約金設定をすることが望ましい。預かり敷金の没収のほかに、即時解約の際の○か月分賃料徴収や建設協力金残金の返済免除、別途独立の違約金設定などがある。テナント仕様ではなくビルイン型の場合には、次のテナント誘致が比較的楽な場合があり、その際には高額な違約金設定は必要がなくなる。違約金の別途支払いが厳しい場合に備え、保証金という名目で金銭を預かっておけば、違約金のとりっぱぐれは少なくなる(保全ができる)。
■オーダーメード賃貸(BTS、テナント仕様賃貸)テナントが必要な面積・規模・デザイン・階高などを指定し、地主オーナーがその仕様で建築してテナントに賃貸することをいう。テナントは建物を自分で購入・建築せずして自分たちが希望する仕様の建物を借りることができるが、オーナーは期間の途中で解約・撤退されると次のテナントを誘致しずらい(面積・規模・デザイン・階高等の汎用性が悪化するため)というリスクを負うため注意を要する。このようなリスクがあるため、一般には、ペナルティ設定を行うことで対処することがほとんどである。特に当該店舗の業績が悪くても会社全体の財務力・資本力があればペナルティを支払われる可能性が高くなるため、大手チェーンとの契約に限定するなど、テナントとしての信用力を考慮しておく必要がある。
■建設協力金テナントのためにオーナーが建物を新築する場合に、テナントが建設のための資金を融資してくれる場合があり、これを建設協力金と呼ぶ。多くの場合建設協力金は無利子である。オーナーは契約期間に応じてこの融資金をテナントに毎月均等返済していくことになるが、一方でテナントはオーナーに毎月賃料を払う必要があるため、この両者を相殺してオーナーは家賃を受領することが多い。賃貸する年数が長くなるほどオーナーは返済するべき建設協力金残額が減っていく。大手チェーン店は建設協力金を提供してくれる場合がありオーナーにとっては融資の資金調達が不要(または少額)になるため取り組みやすい。介護系や小規模テナントは建設協力金を提供しないことが多い。
介護施設
■サービス付き高齢者住宅「サ高住」「サ付き」などと略される、高齢者にとって住みやすいサービスが多く備わっている賃貸住宅。毎月の年金収入を家賃と食事代に充当する方がほとんどである。介護事業者が同じ建物内にケアサービスや訪問介護機能を併設していることも多く、賄い(食事)がついていて介護者が建物内にいる場合には、有料老人ホームと近い形態になる場合がある。オーナーは介護事業者に一括貸しで賃貸借契約を締結し固定家賃が支払われる場合と、住人ごとに家賃が支払われる場合がある。サ―ビス付き高齢者住宅は国土交通省と厚生労働省の二つの省の管轄下に位置しており、建設資金の10分の1の補助金を受けることができる(2016年6月現在)(都内では10分の2が補助されるなどエリアにより一部異なる)。要介護度が高い場合(4や5など)には退去をよぎなくされるなど、「終の棲家」ではないと定義づけている施設がある一方、稼働率アップのために要介護度が高い高齢者を受け入れる施設もある。公共交通機関と近接している必要性が低く、駅から遠い場合やバス便などでも土地活用方法の一手段として利用されている。
■有料老人ホーム介護者が常駐しており安心な生活を送ることができるのが有料老人ホームである。多くの場合、入所者は毎月の年金収入をもって施設利用料支払いに充当する。介護保険に定められているケアサービスを享受できる施設とそうでない施設がある(サービス機能を併設していないなどの場合)。食事やレクリエーションの提供が前提となっており、サービス付き高齢者住宅に比べて団体生活をしている感覚が強い。施設の新設にあたっては、区や市によって毎年の新設可能件数が決まっており、タイミングによっては即座に着工できない場合がある。家賃は一括で介護事業者から支払われる。介護事業者は入所者から高額の入所金を受領することがあるが、一般にオーナーには支払われない(介護事業者が収受する)。公共交通機関と近接している必要性が低く、駅から遠い場合やバス便などでも土地活用方法の一手段として利用されている。
■グループホーム主に認知症の高齢者の方が病気や障害を有するために介護スタッフ等の援助を受けて共同で生活する施設。1ユニット9人であり、1ユニットまたは2ユニット(18人)で出来上がっていることが多い。平屋の施設が多くサービス付き高齢者住宅や有料老人ホームほどの大型の規模ではない。木造のものも多数あるため、総建築費やローン額を抑えやすい。駅前立地である必要がないため、駅から遠い場合やバス便などでも土地活用方法の一手段として利用されているが、アパート・マンションやサ高住・有料老人ホームのように多層階にならないため収入の額は比較的低くなる。
■ショートステイ短期入所生活介護と呼ばれ、数日間のあいだ高齢者を預かる施設。高齢者の機能改善や生活環境の安定を提供するが、同時に家族の介護負担を軽減する役割もある。宿泊(生活)機能があるため、規模としては様々である。連続での利用は最長で30日であり、31日以降は介護保険の給付対象外となる。
■デイケアサービス(通所介護)主に日常生活のケアを行うデイサービスとリハビリを中心に行うデイケアの総称。いずれも居宅サービスではなく施設に訪問してサービスを受ける(通所サービス)。基本的に寝泊りする施設ではなくサービスの提供を行う施設であり、老人ホームやサービス付き高齢者住宅、グループホームほどの規模はない。場合により駅前立地を希望する介護事業者もいる。コンビニやガソリンスタンド跡、マンションの1Fの店舗スペースなどに入居する事業者も多く、必ずしも新築の土地活用と連動するものでもない。
相続税対策
■相続税納税額の削減と土地活用相続税の納税額は土地と建物のそれぞれの資産額から基礎控除額を控除し一定の税率を乗じて計算される。土地を貸したり(借地)、建物を建築して他社や他人に賃貸すると相続税計算上の資産額が減額される仕組みとなっており、建築と賃貸は、高い税額を合法的に減額できる有効な手段となっている。現金を建物に換えるだけでも減額効果はあるが、さらに減額するには「他社や他人に賃貸」する必要があるため、自宅の建て替えだけではなく、少なくとも一部を賃貸にしたり(賃貸併用住宅)、賃貸用アパート・マンションを建築する人が増えてきている。相続税納税額の減額だけに腐心してキャッシュフローが回らなくなったり高額のローンを抱えるなどの本末転倒な取り組みは避けたい。また、税務申告直後に売却するなど節税目的の度が過ぎる場合には税務当局から否認されるおそれもある。
■相続税対策における建築資金ローン相続税対策上「借金」や「ローン」をすると節税になると言われているが、正確には「借りたお金を土地や建物に換えた」ときにはじめて効果が発生する。ローンを借りても現金で保有していれば現金資産とローン(負債)が相殺されるだけであり減額効果は出ない。建築資金について、建築期間中(未竣工)の間は建物としては認められずまだ、効果が発生しないことにも留意する必要がある。
■タワーマンション節税保有している土地に建物を建築する代わりに、保有土地を売却して賃貸用土地建物を購入することも相続税対策となる可能性が高い。賃貸用建物を持つこと=減税効果が高く、土地の共有持分が少ないタワーマンションを相続税対策として購入する例が多い。タワーマンションは一般的なマンションに比べ、棟内の世帯が極めて多いことから、土地の持ち分割合が少なくなるからである。また、家賃と購入金額の高い「高層階住戸」を購入すれば、投下するコストは高いが、1区画あたりの面積が同じ低層階を購入する場合とほぼ同じ(低い)建物評価額が得られる。これにより購入額と評価額の差が大きくなり節税効果が大きくなる。ただし、節税効果のためのテクニックに走り、居住目的や賃貸運用目的など、実態が伴っていない点を指摘されて税務署から否認されたケースがある等、今後のタワーマンション節税動向には留意する必要がある。なお、従前より保有する土地の売却にあたっては譲渡益について所得税が課税される可能性が高い点にも留意が必要である。
■資産の分割方法一般に将来において資産を分割する必要がある場合には共有にしておくとデメリットが大きいと言われる。売却時に共有者全員の合意が必要になるからである。その点から敷地を相続予定の人数分に分割(分筆)しておく方がよいと言われる。その他、戸建て賃貸はそのような分割の自由度を高める方法として「相続税対策の申し子」と呼ばれる場合がある。
戸建て賃貸
■戸建て賃貸のメリット戸建て賃貸は、一戸建てを賃貸する点でアパートやマンションにはないいくつかのメリットがある。①戸建て賃貸は相続させるときに相続人に譲りやすい(相続人の数だけ土地と建物を分割して100%の所有権を渡しやすい)。②エレベータや共有部分などの管理・清掃が不要。③建築のためのローン額がアパートやマンションに比べて比較的小さく済む等のメリットがある。一方で、稼働率の高いアパートやマンションと比較すると収益性に劣るというデメリットがある。
二世帯住宅
■二世帯住宅親や親族と同じ建物に住む場合に、作りが世帯別に分離してある住宅。大型の一戸建て住宅を世帯別に分けて住むイメージ。1つの建物のなかで、水回りの設備が世帯の分だけ作られていることが多いが、玄関まで必ず分けられているかどうかは居住者(施主)によりケースバイケースとなる。相続税対策の観点から、現金→不動産への減額効果とともに、親と「同居」していることで得られる「小規模宅地等の特例」の適用を期待して建てられることが多い。平成27年1月より「二世帯住宅」における面積要件や親との「同居」に関する要件が緩和され、「同居」については、「原則的に、居住空間が構造上分離されていなくてもよい」「親が終身利用権付き老人ホームに入居していてもよい」等と定められたことから、小規模宅地等の特例を適用しやすくなった(詳細は税理士等の確認が必要)。他人・他社に賃貸しなくても小規模宅地等の特例により減額が可能である場合にぜひ検討したい建築方法。
賃貸併用住宅
■賃貸併用住宅自宅を建築するときに賃借人が住める区画も同じ建物内に作る。これにより、毎月の住宅ローンの返済にあたり、賃借人の毎月の家賃を充当することで、ローン返済額の負担を軽減できる仕組みが出来上がる。自宅を1Fにする場合と、2Fや3Fにする場合とがあり、施主の好みによる。世帯の数だけ玄関ができる。全体の建物延べ床面積の過半を自宅用途にすれば、金利の低い住宅ローンを利用することができるが、過半を超えると住宅ローンは利用できずアパートローンや事業用ローンを利用することになる。自分で保有する賃貸アパート・マンションの1室に自分で住む場合と近いが、自宅が過半を占めなければ住宅ローンが利用できず、住宅ローン控除制度も利用できなくなる。

|